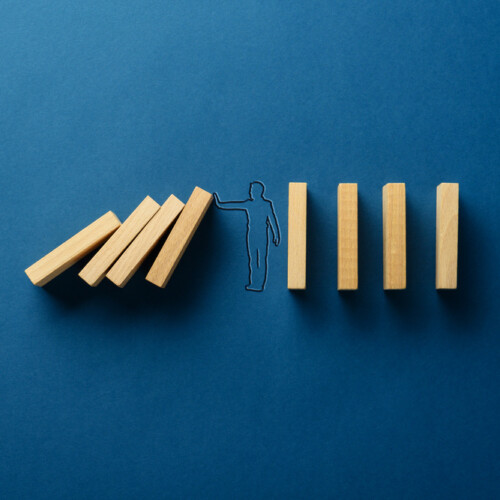【特別対談ブログ(前編)】〜教育史から読み解く、アメリカの教職に女性が多い理由。〜

【特別対談ブログ(前編)】慶應義塾大学 佐久間亜紀教授
〜教育史から読み解く、アメリカの教職に女性が多い理由。〜
本日のブログでは、慶應義塾大学の佐久間亜紀教授との対談記事をお送りします。
ビジティングスリサーチャーとしてスタンフォード大学に従事される佐久間教授に、ご専門の「日米の教育史」についてお話しいただきました。
星友啓(以下、星):アメリカの中等教育の先生は、かなり女性が多いですが、これにはどのような理由があるのでしょうか。
以前同僚と、戦時下において教育が家庭のものであったとき、教えるということは女性の役割のようになっていたからではないかと推測していましたが、実際のところはどうなのでしょうか。
佐久間亜紀(以下、佐久間):現在、アメリカの小学校では9割以上、中学・高校でも6〜7割の教員が女性です。
いま「戦時下」とおっしゃいましたが、実はこの女性が高い割合を占めている構造は、南北戦争の前から既にありました。
それは、近代的な「学校の成り立ち」と深い関係があります。
アメリカが国をつくっていく時に、やはり移民から始まった国なので、「私たちはアメリカの国民だ」と一つにまとまるスピリットを形成していくことが、国家的な課題でした。
そこで、お金持ちが通える私立学校に加えて、一般的な大衆が無償で通える「コモンスクール」をつくろうというのが、国家的な事業になったのです。
ところが、誰でも通える無償の学校をつくろうとなると、先生は必要だけれどもお金はない。
そこで、政治家たちがとったのが「安く使える女性を雇えばいい。」という戦略だったのです。
コモンスクールを広める運動の前は、教えることは男性の仕事でした。
女性はそもそも人権を認められていないので教育も受けていなかったし、あり得ない話だったのです。
だから、「女が教育者になるなんて考えられない」という大反対が教育界では起きていました。
けれども、背に腹は代えられず、「教員の待遇を上げて優秀な人材を学校業界に獲得するよりも、待遇が安いままで、それでもいいから働いてくれる人の数を揃えればいい」という考えから、19世紀初頭から、教育界では低賃金で使える女性の労働力が当てにされるようになったたという流れになります。
教育者の低賃金問題
星:もう一つ、大きなトピックとして教師の「賃金の低さ」があると思います。
アメリカでは、同じような学位を持っていても他の分野で働いている人に比べて20〜30%給料が低いという現状があります。
それも先生がお話してくださった歴史の流れが影響しているのでしょうか。
佐久間:まさにその通りです!
ここが面白いところなのですが、さきほどお話した男性政治家たちの戦略に、女性リーダーたちが、自ら乗っかって、「女性は低賃金でも喜んで働きます」と説いて回ったのです。
例えば、女性の高等教育の開拓者と称えられているエマ・ウィラードという女性は、「愛に満ちた女性こそが、子どもを育てる教師に向いている」と訴えました。「アメリカという神さまに愛された特別な共和国を、よりよい国にするための大事な市民を育てるのだから、教職は重要な仕事だ」というのです。そして、「女性は、子どもを育てる大事な仕事を担うのだから、女性もきちんとした教育を受けられるようにしなければならない」と力説しました。
そして、例えばいまのマウント・ホリヨーク大学の創始者メアリ・ライアンは、「教職は、神に仕える聖なる仕事だから、女性教師たちは給料が欲しいなどと言ってはならない」という考え方を、主張していました。
つまり、女性自らが、私たちなら安く使えますよ、だから雇ってね、そのかわり女性も教育を受けられるようにするべきだ、という論理を積極的に広めていったのです。
政治家の思惑と、女性の思惑はみごとに合致し、このキャンペーンは大成功を収めました。当時、女性が現金収入を得られる仕事がほとんどなかったのに、女性は教職につけるようになりました。そして女性たちは、教師を育てるために新しく作られた「師範学校」という学校で、中等教育や高等教育を受けられるようになったのです。
ところが皮肉にも、アメリカの公立の学校とその先生たちは、200年後も変わらず、19世紀初頭に作られた考え方に苦しめられる結果がもたらされてしまった、ということになります。
つまり、「教職は聖なる職業なのだから、給料を上げろなどというのはふさわしくない、子どものためには自己犠牲的をいとわず、安い賃金でも文句を言わずに働くべきだ」という考え方が、今も続いているということです。
今パンデミックでアメリカのパブリック・スクールの先生方はまさにその状況を強いられています。
十分な手当てもされず、でも「子どものためだから」と言われて、自分たちの安全や健康は後回しにされて疲弊していく。
「子どものために」という言葉を持ち出されて何となく納得させられてしまう、あるいはその論理を内面化して自ら身体を壊すまで無理して働いてしまう、という状況が19世紀の初めから今も続いているということです。
教育学部を取り巻くスティグマ(偏見)
星:教員不足でポストが空いているという問題についてはどうお考えでしょうか。
佐久間:大きな理由として、教員を養成する機関が「スティグマ(偏見)」を持たれているということがあります。高い学歴を持つような優秀な人(特に男性)が、教員になるなんてもったいない、もっといい職業に就けるのに、という見方が広まってしまっているのです。
そこでも、ジェンダーの問題が大きく関わっています。
19世紀の初頭に、師範学校(今でいう、大学の教育学部)を作ろうという議論を男性政治家や教育者たちが熱く交わしていた時には、子どもたちを教える大事な仕事のプロを育てるということで、期待と志は高くありました。もちろんプロとしての教職には男性がつくという前提での議論です。。
しかし、実際には、さきほどお話したように、師範学校が普及する頃には教職の女性化が進んでいたのです。「子ども相手に教えるなんて、女の仕事だよ」という固定概念が生まれ、そしてお給料も低いままで待遇の改善もなかった。
だから、教える仕事が女性の地位の低さと結びついてしまったのです。
実情としても、教職につきたいと師範学校に入ってくるのは、中等教育をまともに受けていないような女性でした。師範学校のファカルティは、養成期間を長くして質の高い教育をしたいとあれこれ工夫を重ねますが、そうすると学費が高くなり、優秀な受験生がこなくなってしまう。卒業して教職についても、それほど高い給料をもらえないとわかっているから、割にあわなくなってしまうからです。
そのような葛藤がある中で、当時から師範学校、教育学部は質の高い教員を育てるのに失敗しているというレッテルが張られて、十分な社会的支援は与えられず、バッシングだけが続いてきました。
政治家が汚職を重ねても、政治経済学部のせいだという批判は聞かれませんし、経済が不況に陥っても、経済学部が優秀な経済人を輩出していないからだ、という批判は聞かれません。不況が起こるのにはいろんな要因が絡まって起きているのであって、経済学部だけのせいで不況が起こるわけではない、という考え方が、広く共有されているからです。しかし、学校に問題が起きると、学校や教職をとりまく社会的な問題構造は無視されて、なぜか全部が教育学部のせいだと、教育学部がきちんと教員を養成していないから学校に問題が起きているんだ、という批判の大合唱がおきるということが、19世紀からずっと続いているのです。
星:確かに、スタンフォードでさえ、他の教授たちに「どうせ教育学だろ」と見下げたように言われることがあります。
佐久間:はい。ジェンダーの他に偏見を持たれる要因として、子どもや福祉に関連する仕事は、政治や経済や外交に関する仕事よりも、低く見られるという社会構造があります。例えば、医学部でも小児科医は一段低くみられます。子ども一人を治療しても、身体が小さくて必要な薬量は少ないため、病院の利益が上がりにくいことが関連しているのです。そもそも子育てや介護は、公的領域の問題としてではなく、できる家庭が担うべき私的な問題なのだと位置づけられているのです。
ただし、子どもを、「国力や軍事力を担う人材」「経済発展を担う人材」という文脈でとらえる時だけは、政治や経済や外交に関する問題として、急に教育が重要な問題としてフィーチャーされるのです。
注意しなければならないのは、この「国力や経済力のための人材養成」という観点からの教育論では、重い障害や病気と共に生きる子ども達や、さまざまなハンディを負った子ども達など、官僚や経済人や軍人になる可能性が低い子ども達の学びや育ちは、ほとんど無視されがちだということです。
一方、近年の教育学では、人間一般の学びや育ちを、広く対象にすることが大前提となっています。人間は、赤ちゃんとして生まれ、長い年月を経て学び育ち、社会に出て政治・経済活動をします。そして、仕事を辞めたあとも第二の人生を歩み、死ぬ最後の瞬間まで、何かを学び続ける存在なのです。
「生産性の高い人材を、いかに効率的に育てるか」という観点を最優先にする人々からすれば、こうした教育学の視野の広さは、悠長すぎて、役にたたないものに見えてしまうのでしょう。こうした人間観の違いも、経済学部や政治学部の人たちから、教育学が低く見られてしまう要因の一つになっているのです。
ですが、逆の立場からみればそれは、冒頭でお話したように、近代国家を強くするために始まった教育学を、「国のための教育」から「一人一人の子どものための教育」「すべての子どもの学びを支える教育」へと転換させようとしてきた、心ある無数の教師達の、苦闘の成果としての教育学でもあるのです。
詳しく知りたい方は、拙著『アメリカ教師教育史』(平塚らいてう賞受賞)や、私の恩師であるスタンフォード大学名誉教授のDavid F.Labaree先生のご著書“The Trouble with Ed Schools”を、是非お読みになってみてください!
※次回のブログでは、続編として、「日本の教育の歴史と現状」についてお話いただきます。ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。
【対談ゲストプロフィール】
慶應義塾大学 佐久間亜紀(さくま・あき)

1968年東京生。早稲田大学教育学部卒業。東京大学大学院教育学研究科博士課程修了(博士(教育学)。 東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター准教授などを経て、現職。 専門は、教育方法学、教師教育論。 日本教育方法学会全国常任理事、日本教師教育学会理事。 教師の力量形成を研究・実践し、各地の学校現場で授業づくりに取り組むとともに、対人支援専門職(看護・介護職など)の人材育成について講演やワークショップを行っている。授業研究会「第三土曜の会」主宰。 著書に『現代日本の教師』(放送大学教育振興会、2015年)など。